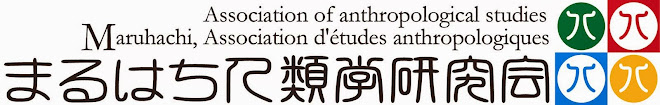下記の要領で研究会をおこないます。
皆様ふるってご参集ください。
日時:7月2日(土):13時30分-17時20分頃 終了後懇親会あり
場所:南山大学名古屋キャンパス人類学研究所 1階会議室
http://www.nanzan-u.ac.jp/JINRUIKEN/index.html
沖縄の祭祀研究はどこへいったのか?
――古典研究とポストコロニアル理論を架橋する試論としての『移動』と『祭祀』――
13:30-13:40 趣旨説明
13:40-14:20 越智郁乃(広島大学・特別研究員)
記憶のメディアとしての墓と人-現代沖縄における墓の移動を事例に-
14:20-15:00 平井芽阿里(京都大学大学院・グローバルCOE研究員)
本土の沖縄系コミュニティに見る「沖縄」表象 愛知県在住の沖縄県出身者の事例
15:00-15:40 吉田佳世(首都大学東京大学院・博士後期課程)
女性の移動としての離婚/再婚――現代沖縄社会における女性の死後の処遇をめぐる新たな実践の出現――
コメント
15:50-16:05 田中真砂子(お茶の水女子大学・名誉教授)
16:05-16:20 村松彰子(相模女子大学・専任講師)
討論
16:20-17:20
沖縄の祭祀研究はどこへいったのか?
――古典研究とポストコロニアル理論を架橋する試論としての『移動』と『祭祀』――
文責:吉田佳世
◆ 本企画の目的
本企画の目的は、かつてあれほどまでに興隆した沖縄の祭祀研究(村落祭祀・祖先祭祀)を、いかにポストコロニアル批判以降の現代の文化人類学(以下、人類学と表記)・民俗学の地平に位置づけるのかを模索・検討することにある。
これまで沖縄は、祭祀のみならず親族、世界観など人類学的・民俗学的研究の要であった[e.g.馬淵1955(1974)、村武1975]。現在でも、日本の「周辺」にあるというその位置性故に、ポストコロニアル批判や研究の焦点的な事例とされる地域である[e.g.村井1992、冨山1990、菊池2010ほか]。ところが、ポストコロニアリズムの興隆の背後で、沖縄の祭祀は古典的研究主題として位置づけられ、研究主題としては周辺化されているという現状がある。しかし、沖縄の祭祀は、「本土化」と呼ばれる以上の急激な社会変化のなか、いまなお人々の関心を集め、創造的な実践が行われている舞台である。このことを考えると、沖縄の祭祀研究は、決して過去の研究主題ではなく、様々な点で現在の人類学・民俗学の動向と切り結ぶ点を有していると考えられる。
本企画では、グローバル化の一局面であるヒトの移動をとりあげ、そのなかで伝統的文化事象としての位置づけをもつ沖縄の祭祀が、現代沖縄社会という文脈のなかでいかに維持され、再構築されているか個別具体的に明らかにする。発表と討論を通じて、これまでほとんど光が当てられてこなかった祭祀の様相を描き出すとともに、今後いかなる人類学・民俗学の議論に位置づけることができるのかを模索していきたい。
◆ 沖縄研究の流れ――明治期から現代まで
原による沖縄研究の時代区分に依拠しながら[cf. HARA 2007]、本稿では大きく三つの時代に区分する。第一期は、明治期から1950年代に中心的に行われた、日琉同祖論を背景とした文化周圏論にもとづく日本民俗学的研究である。日琉同祖論とは、日本本土(ヤマト)と沖縄(琉球)の民族一体性を強調する仮説のことであり、日本民俗学は、双方の文化的同一性を学術的に立証することを通じてこれに寄与していたといえる。第二期は、1950年代から1980年代前半までの、主に日本本土出身の研究者によって行われた人類学的研究である。この時期は、第一期とは対照的に、沖縄を日本本土や中国の文化の折衷としてではなく、独自の文化として捉えることを目的としており、フィールドワークを通じてひとつの村落を集中的に調査するという研究手法が主流となった[新井1970]。そして、最後に、1980年代後半から現在まで、ポストコロニアリズムが興隆した第三期である。第三期は、先行研究批判と新たな研究主題の掘り起こしが同時に進められたため、ひとつの研究傾向を抽出することは難しいが、対抗的な沖縄人アイデンティティの構築や、観光や芸術、基地文化などの複数文化接触領域(コンタクト・ゾーン)に多く研究関心が向けられているといえる。
本企画のテーマである祭祀が、人類学および民俗学において積極的に議論されたのは、第二期のことである。この頃、西欧由来の構造=機能主義人類学の影響をうけ、祭祀にまつわる諸観念(祖先観、霊魂観、他界観)と祭祀集団原理やその実践との対応関係が注目された[e.g. 大胡1973ほか]。とりわけ、祖先祭祀とそれを担う祭祀集団である門中やその組織化と深いかかわりをもつ社会関係は、沖縄の出自集団として注目され、議論が集中する主題であった[中根1962、東京都立大学南西諸島研究委員会1965、田中1982、渡邊1985ほか]。このような研究手法がとられたのは、当時、祭祀の研究は、事例として扱った祭祀や祭祀集団の個別的理解のみならず、より広く当該地域レベルでの親族・社会システムの解明に寄与できると想定されていたからである。また、この頃は、日本本土出身の人類学者がこぞって沖縄調査を行った時期でもある。そのため、数百にもおよぶ沖縄の祭祀を主題とするモノグラフが刊行されたのである。
◆ ポストコロニアル批判とその問題点
沖縄の祭祀研究の退潮は、単にポストコロニアリズムによる先行研究批判のみに起因するものではない。人類学における親族研究の退潮という学術的な要因はもちろんのこと、日本全体が高度経済成長をむかえ、その経済力をもとに日本本土出身の人類学者が海外へと研究地を拡大していったこと、沖縄社会自体もその在り方を変えたことなど、学術的動向と社会的動向とが絡み合いながら生じたものであるといえる[吉田 2008]。そのなかで、ポストコロニアリズムによる先行研究批判は、人類学・民俗学がこれまで行ってきた祭祀研究の問題点をより具体的に明らかにしたとして評価することができる。
ポストコロニアリズムがこれまでの沖縄の祭祀研究に対して投げかけた批判は、民族誌論、沖縄人のアイデンティティ、基地といった現代的諸問題、研究者の位置性・政治性など多岐にわたっている。なかでも影響力のあったポストコロニアル批判としては、人類学・民俗学的研究の「本土化による荒廃のない」伝統的文化事象や村落共同体への選好を批判した太田の指摘であろう。太田によれば、人類学的な沖縄研究が、集落単位でのモノグラフィックな調査が主流を占めており、より原初的で、自己完結的な集落を選定してきたのではないかと述べている。彼は、こうした人類学の研究手法を、文化を消えゆくものとして語ろうとする意志であるとし、クリフォードに習い「エントロピックな語り」であると批判した。そのうえで、対象社会の人々の実践を文化の創造過程として捉える事を提唱し、従来の研究において見過されがちであった観光、開発、芸術など異種混淆性に着目した新しい研究主題を掘り起こす流れを作りだしたといえる[太田1998]。
確かに、第二期のフィールドワークによってひとつの集落を集中的に調査するという研究手法の結果、外部からの影響、たとえば、より巨視的な歴史的・政治的な脈絡との関わりを十分考慮していなかったという問題点は、本企画のテーマである移動という問題にも関わってくる指摘である。しかし、それが「エントロピックな語り口」であったかどうかということについては疑問が残る。とりわけ、第二期のモノグラフを詳細に検討すれば、沖縄の祭祀を沖縄戦後の人々の示す創造的対応として記述してきた研究も少なくないからである[e.g. 村武 1971]。先行研究をエントロピックな語りとして先行研究を一枚岩化し、沖縄の祭祀を古典的研究として周辺化するという昨今の沖縄研究の現状は、逆に、これらの事象を非歴史的、無時間的なものとして固定化する危険をはらんでいるのではないだろうか。
◆ 移動を考える
本企画では、日本本土において形成される移住者たちの沖縄系コミュニティ(平井)、沖縄戦後の都市形成と交通網の発展による向都離村(越智)、離婚や再婚による女性の家間移動(吉田)など、さまざまな現代的局面をヒトの移動として捉えていく。そのうえで、「社会変容によって伝統文化がかように変化した」というような、近代と伝統とを排他的な二分法によって実態的に捉えることから逃れられるような研究発表を目指していく予定である。
◆ 参考文献
新井ウィリアム 1970「中国および日本のメモリアリズムと祖先崇拝」『社』3(1):1-9。
大胡欽一1973「祖霊観と親族慣行――琉球祖先崇拝の理解を目指して」日本民族学会(編)『沖縄の民俗学的研究――民俗社会と世界像』pp.169-206.東京:民族学振興会。
太田好信1998『トランスポジションの思想――文化人類学の再想像』世界思想社。
菊池夏野 2010『ポストコロニアリズムとジェンダー』青弓社。
高良倉吉1996「琉球史研究からみた沖縄・琉球民俗研究の課題」『民族学研究』61(3):463-467。
田中真砂子 1982「出自と親族」渡邊欣雄(編)『現代のエスプリ3親族の社会人類学』pp.83-108.至文堂。
東京都立大学南西諸島研究委員会(編)『沖縄の社会と宗教』東京:平凡社。
冨山一郎 1990『近代社会と「沖縄人」――「日本人」になるということ』日本経済評論社。
中根千枝1962「沖縄の社会組織 序論」『民族学研究』27(1):1-6。
馬淵東一 1955(1974)「沖縄先島のオナリ神」『馬淵東一著作集3』pp.123-45. 世界思想社。
村井 紀 1992(2004)『南島イデオロギーの発生――柳田國男と植民地主義 新版』岩波書店。
村武精一 1971「沖縄本島・名城のdescent・家・ヤシキと村落空間」『民族学研究』、36(2):109-150。
―――― 1975『祭祀空間の構造――社会人類学ノート』東京大学出版会。
渡邊欣雄 1985『沖縄の社会組織と世界観』新泉社。
吉田佳世 2008「沖縄の祖先祭祀と社会組織に関する研究動向――1960年代以降の位牌祭祀研究を中心に」、『社会人類学年報』34:177-201。
HARA, T. 2007“Okinawan Studies in Japan, 1879-2007.”Japanese Review of Cultural Anthropology 8:101-136.
記憶のメディアとしての墓と人-現代沖縄における墓の移動を事例に-
広島大学・特別研究員 越智郁乃
本発表では現代沖縄の墓の移動を事例に、墓における外在化された記憶に注目しながら、墓と人との関係について論じることを目的とする。
沖縄社会は本土日本と比べて特異的に祖先信仰が発達した地域であり、葬墓制及び祖先祭祀を通じた祖先観や、祭祀を支える親族集団の特色が学術的に注目されてきた。そこでのテーマは、死者がいかに儀礼を経て祖先へと変化して子孫を守る存在になるかという柳田國男以来の民俗学における祖先祭祀の議論であった。他方、社会人類学的には、親族組織における近代以降の父系血縁イデオロギーの強化が注目され、その動態が中心的なテーマであった。しかし個々の地域における祭祀儀礼や親族組織の多様性から、「沖縄」としての一般化を拒む研究者らによる異議が呈された。以上の研究に対し二点の問題が挙げられる。(1)人口流動や社会的経済的な変化による影響を考える視点が希薄であり、どこで生きてどこで死ぬかということが問われる現代の死生観の問題に添っていない。(2)祖先祭祀を通じた祖先観や祖先と子孫の繋がりである系譜観に関して、構造的な研究だけではなく、生者側の記憶や情緒により不断に作り替えられる側面に注目した研究の必要がある。
上記の問題点を踏まえ発表者が注目したのが、墓の移動をめぐる人々の語りと実践である。沖縄本島への政治経済的な中心化による都市化と人口移動の活発化を背景に、集合墓地と造りの簡易な新型墓が増加し、移住者が故郷にある墓を都市部に移動するという事象が現在認められる。新型墓は新規造墓の大多数を占めるが、研究者や現地の人々により、亀甲墓に代表されるような斜面に掘り込み墓室を設けた「伝統的な墓」の枠内からは排除されてきた。そこで都市部に移住した離島出身者の祖先祭祀に関する資料を収集し、墓の移動に表象される死者への祈りの場の変化が人々に与える影響を明らかにしながら、既存の祖先観、系譜観研究の批判的検討をこれまで行ってきた。
本発表では、墓の移動過程における骨や石などの「モノの処遇」に関する資料を中心に取り上げる。元の墓からの新しい墓に移動する際に持ち込まれるもの、捨てられるもの、創られるものなど、墓におけるモノを媒介して人々の記憶が外在化される過程の分析から、移住者の故郷観と死者との繋がりが新たな墓にいかに昇華されるか、そして生者の生活にいかなる影響を与えるかということについて考察したい。
本土の沖縄系コミュニティに見る「沖縄」表象 愛知県在住の沖縄県出身者の事例
京都大学大学院・グローバルCOE研究員 平井芽阿里
本研究の目的は愛知県の沖縄系コミュニティの「沖縄」表象について個々人の民俗宗教の日常的実践から多元的に考察することである。
本発表では、本土在住の沖縄県出身者が結成した各種団体を「沖縄系コミュニティ」とする。本土における沖縄系コミュニティには、郷友会、青年会、婦人会、芸能団体などがあり、各県ごとの沖縄県人会が全ての団体を総括している。愛知県では愛知沖縄県人会連合会がこれにあたり、1960年代以降、日本本土への復帰運動を背景に結成されるなど政治的組織として機能してきたという特徴がある。現在では本土に居住する沖縄県出身者および各種団体の名称、氏名(代表者)、住所登録や管理などを行い、個人データの一部は沖縄県庁とも共有している。他にも、このような沖縄系コミュニティから派生した、出身地ごとに組織される模合(相互扶助的な金融組織)や同窓会といった団体もある。
既存研究の多くは、このような沖縄系コミュニティを分析対象とし、本土における「沖縄」や「沖縄人」像を描いてきた傾向にある。一方で、沖縄県出身者が結成するコミュニティは、必ずしも県人会や郷友会といった組織に限られるわけではない。例えば、年数回、出身地で行われる村の儀礼に参加するために加入する祭祀組織や適齢を迎えた者が行う特殊儀礼へ参加するために一時的に組織された同窓団体などもある。さらに、身内の不幸や原因不明の病気、事故や怪我などの災因が解決されない場合に、故郷から霊的職能者を招請し、問題解決を図るための「集まり」などもある。沖縄県人会に所属する個々人が日常的に実践する民俗宗教に着目すると、沖縄県人会に登録されている「沖縄人」は、各種団体に所属するだけでなく、故郷の祭祀組織にも加入し、突発的な集まりにも参加をする。つまり、本土在住の沖縄県出身者は複数の、異なる次元で存在する様々な沖縄系コミュニティに重層的に参加し、コミュニティごとに異なる「沖縄」を表象している。同時に、本土の沖縄系コミュニティには、沖縄本島、宮古・八重山諸島各地の出身者だけでなく、沖縄県出身者の2世や3世、「沖縄ファン」の本土出身者も含まれている。即ち、一つのコミュニティに表象される「沖縄」もまた一様ではなく、同一の「沖縄人」が所属しているわけでも、同一の「沖縄」が表象されているわけでもないといえる。
以上を踏まえ、本発表では個々人の民俗宗教の日常的実践を通して愛知県の沖縄系コミュニティの「沖縄」表象について考察するものである。
参考文献
愛知の沖縄調査会編2009『愛知の中の沖縄 先人達の足跡を求めてVOL.1』愛知沖縄県人会連合会
大阪人権博物館編『ヤマトゥのなかの沖縄』大阪人権博物館
沖縄県教育委員会編1974『沖縄県史 第7巻 各論編6』沖縄県教育委員会
ジェラード・デランティ著、山之内靖他訳2006『コミュニティ グローバル化と社会理論の変容』
NTT出版
田辺繁治、松田素二編2002『日常的実践のエスノグラフィ 語り・コミュニティ・アイデンティテ
ィ』世界思想社
田辺繁治2008『ケアのコミュニティ−北タイのエイズ自助グループが切り開くもの』岩波書店
桃原一彦1997「沖縄を根茎として」奥田道大編『都市エスニシティの社会学−民族/文化/共生の意
味を問う』ミネルヴァ書房
冨山一郎1990『近代日本社会と「沖縄人」』日本経済評論社
牧野眞一2002「沖縄の同郷者集団−県人会活動を中心に−」松崎憲三編『同郷者集団の民俗学的研究』
岩田書院
山口覚2008『出郷者たちの都市空間−パーソナル・ネットワークと同郷者集団−』ミネルヴァ書房
女性の移動としての離婚/再婚
――現代沖縄社会における女性の死後の処遇をめぐる新たな実践の出現――
首都大学東京大学院・博士後期課程 吉田佳世
本発表は、沖縄戦以降の沖縄社会における離婚あるいは再婚の増加を、女性の移動の一局面としてとらえ、その結果生じている女性の死後の処遇をめぐる実践を考察することにある。結論を先取りしていえば、本発表では、現代沖縄社会における女性死者に対する新たな弔い方の出現を、「伝統的」な祖先祭祀の「近代化」による変容として記述するのではなく、沖縄戦後の政治的・歴史的過程のなかで、伝統的な祖先祭祀制度の確立と、近代化による祖先祭祀からの逸脱が、同時並行した状況として捉える事を目指したい。
沖縄における女性の死後の処遇が、日本本土に比して特徴的であることは、先行研究においても着目されてきたことである。たとえば、位牌・墓の祭祀における女位牌(イナググヮンス)の禁や冥界婚(グソーヌニービチ)は、その最も顕著な例であろう。簡単に説明しておけば、女位牌の禁とは、家や位牌を女性が婿養子を迎えるなどして後を継ぐこと、あるいは、女性が家を創設し初代先祖になることを強く忌避する慣行のことである[竹田 1976、萩尾1986]。他方、冥界婚とは、特に離婚を経験した女性や、子ども(特に男児)を産むことができず生家に戻された女性などの位牌や遺骨を、夫婦あるいはそれに準ずる関係にあった男性のもとへ移動させる儀礼のことである[桜井1973]。すなわち、沖縄の祖先祭祀制度において、女性は、結婚して生家を出たうえで、婚家において家や位牌の継承者となる男児を確保することが強く要請されているのである。先行研究においては、沖縄の女性をめぐる特徴的な慣行を、男系血縁を重視する制度との関連で理解されることが一般的であった。しかし、女性の死後の処遇に関しては、依然として疑問も多く残されたままである。それは、本発表のテーマである、離婚や再婚の過程で複数の婚家と目される家とかかわりをもった女性はいかに弔われるのかという疑問ももちろんそのひとつである。
本発表では、具体的な事例を通じて、離婚や再婚を経験した女性の死後の処遇をめぐる実践を明らかにするとともに、このような実践が生起した背景を、近代化にともなう女性のライフコースの多様化という問題だけでなく、男系血縁原理の伝統化という観点からも考察を加えたい。つまり、男系血縁原理が沖縄戦後の歴史的・経済的状況によって強化された帰結として、女性の死後の処遇をめぐる多様な実践が生起したという考え方である。それを通じて先行研究上の問題点である、非歴史的・固定的表象を修正するとともに、近代化が、当該地域やそこに暮らす人びとに非均質的な影響を与えているという実態を明らかにしていきたい。
◆ 参考文献
桜井徳太郎1973『沖縄のシャーマニズム――民間巫女の生態と機能――』。
竹田 旦 1976「祖先祭祀――とくに位牌祭祀について」九学会連合沖縄調査委員会(編)『沖縄――自然・文化・社会』pp.165-180.弘文堂。
萩尾俊章 1986「位牌祭祀と禁忌――沖縄本島中部における事例研究」『沖縄民俗研究』6::21-33。