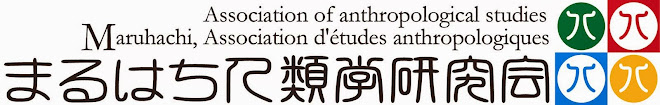みなさま 日に日に、寒さが増していますが、いかがお過ごしでしょうか。 このたび、以下の日程で、第9回目の研究会を行うこととなりました。 お誘いあわせのうえ、ぜひ、ご参加ください。 なお、今回は、中部人類学談話会との共催です。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 日時:2011年12月3日(土曜)13時30分より 場所:椙山女学園大学 星が丘キャンパス 現代マネジメント学部 地階 001教室 (名古屋地下鉄東山線星ヶ丘駅下車 徒歩5分) 『経済から宗教をみる―「宗教組織の経営」についての文化人類学的研究―』 13:00 開場 13:30~13:40 「中部人類学談話会とまるはち人類学合同企画」趣旨説明 13:40~13:50 『経済から宗教をみる―「宗教組織の経営」についての文化人類学的研究―』趣旨説明 13:50~14:40 藏本龍介『〈都市〉を生きる出家者たち―上座仏教社会ミャンマー・ヤンゴンの僧院経営―」 14:40~15:30 清水貴夫『タリベとコーラン学校のモビリティ:ブルキナファソの事例から』 15:30~15:45 休憩 15:45~16:15 コメンテーター(15分×2) (南山大学人間文化研究科教授 坂井信三、日本学術振興会特別研究員(PD)門田岳久) 16:15~17:00 質疑応答(フロア) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
経済から宗教をみる
――「宗教組織の経営」についての文化人類学的研究――
◆本企画の背景:実践宗教研究の系譜
キリスト教・イスラーム・仏教など、いわゆる世界宗教を対象とした学術研究は、長らく文献学的な教義研究がリードしてきた。しかし教義としての宗教と、信徒によって実際に生きられている宗教は異なる。こうした問題意識から1950年代以降、人類学的な世界宗教研究が始まる。「教義」ではなく「実践」を解明すること。これが現在に至るまで、人類学的な世界宗教研究の一義的な目的であるといってよい(cf. Leach ed. 1968)。
それでは実践をどのように分析するか。この問題について、先行研究において重視されてきたのが、信徒の生きる社会的コンテクストである。信徒はそれぞれのコンテクストにおいて、教義を様々に理解・解釈し、実行する。こうした理解から実践は、コンテクストとの関わりにおいて分析されてきた。たとえば初期の研究(1950~80年代前半)において注目されたコンテクストとは、その社会に固有の信仰体系であった。つまり現実に展開している実践は、外来の教義(大伝統)と土着の信仰体系(小伝統)が融合した結果生じたものであると考えられ、両者の構造的な関係の解明を目指すシンクレティズムの議論が盛んであった(ゲルナー 1991; Tambiah 1970など cf. Redfield 1956)。
しかしこのようなアプローチは実践を画一的・図式的なものとしてしか描けない。こうした反省から近年の研究(1980年代後半~現在)においては、政治・産業構造の変化、都市化、近代教育の普及、交通・通信の発展といった大きな社会変動という動態的なコンテクストに注目が集まるようになり、多様で新しい実践がそうしたコンテクストと結びつけられて分析されている。たとえばキリスト教圏における公共宗教の復興(カサノヴァ 1997)、仏教圏における改革主義的な仏教運動の展開(ゴンブリッチ&オベーセーカラ 2002)や仏教儀礼の祭礼化(田辺編 1995)、イスラーム圏における急進的な政治運動の登場(大塚 2000)や、再ヴェール化に代表されるようなイスラーム復興現象(大塚編 2002)などである。
しかしこれらの諸研究は、観察されたミクロな実践とマクロな社会的コンテクストを安易に結びつける傾向にあり、特定の社会的コンテクストからなぜそのような実践が析出するのかという問題を、十分に説明できているとは言い難い。したがって宗教の世俗化/再活性化、個人化/公共化といった相反するイメージが、同じ社会変動というコンテクストによって説明されるという状況になっている。
このようにこれまでの実践宗教研究においては、実践を取り巻く社会的コンテクストが重視されてきたが、そうしたコンテクストが具体的にどのように実践の現れ方を規定しているのか、よくわからない。その原因は、実践とコンテクストの距離が離れすぎているところにあるように思われる。今・ここにおいて、なぜこのような実践が行われているのか。その核心に迫ることができるようなコンテクストの設定、分析枠組みが必要である。
◆本企画の視点:経済から宗教をみる
この分析枠組みとして本企画で提示したいのが、実践を取り巻く経済的な問題に注目するという方法である。ここでいう経済的な問題とは、一言でいえばカネの問題である。現実の社会で活動するためには、様々なモノやカネといった財が必要である。それは宗教実践も例外ではない。教義がどれほど高邁な理想を掲げていたところで、実際に何をどのようにできるかは、経済的な問題に大きく左右されている。その一方で、各宗教には財をどのように獲得・利用すべきかについては、何らかの教義的な制約(経済倫理)がある。つまり宗教的な理想を実現するためには、財と自由に関わっていいわけではない。
ここに宗教実践の大きなジレンマが存在している。つまり教義に固執すれば、経済的な現実にうまく対処できない可能性がある。逆に、経済的な現実への対処を優先すれば、教義を逸脱しかねない。こうした教義的理想と経済的現実のジレンマに、信徒たちは実際にどのように対応しているのか。そしてその中からどのような実践を紡ぎ上げているのか。こうした信徒の日常レベルに生じる経済的な問題こそが、信徒の実践により密接に関わる社会的コンテクストである。このように本企画では、実践を教義的理想と経済的現実のせめぎ合いの中から析出するものとして捉え直し、その実態を解明することを試みる。
このような方法論をとることは、以下の二つの点において人類学的な宗教研究に貢献しうると考える。第一に、経済的な問題に注目することによって、宗教実践のダイナミズムを浮き彫りにしうる。教義というプログラムが、現実の社会においてどのように実行されるかを左右する大きな要因は、【教義的理想⇔経済的現実】というせめぎ合いにある。したがってこのせめぎ合いに対する信徒たちの試行錯誤を描き出すことによって、一つの教義から多様な実践が表出していく原理・メカニズムを理解することができる。
第二に、経済的な問題に注目することによって、宗教と経済の相互関係をより具体的に捕捉しうる。宗教(教義)という観念的領域と、経済という唯物的領域はどのような関係にあるのか。この問題についてはK.マルクスとM.ウェーバーの古典的な議論がある。マルクスは物質的経済的土台である下部構造が、政治的・法的・思想的諸形態である上部構造を規定する、つまり「経済が宗教を規定する」と主張した(マルクス 1956など)。それに対してウェーバーは、宗教は経済に規定されない独自の生命をもち、それゆえに「宗教が経済に影響を与えうる」という発想から、近代における資本主義経済システム誕生という大問題に挑んだ(ウェーバー 1989など)。
しかしこれらのいわばマクロな理論は、現実を生きる信徒そのものへの視点を欠いている。ミクロなレベルからみたとき、信徒の実践は、教義的理想もしくは経済的現実のどちらかに規定されているわけではなく、二つのベクトルのせめぎ合いの中にある。つまり宗教と経済の相互関係は動態的で未決定である。したがって、教義的理想と経済的現実がせめぎ合いの中からどのような実践が析出しているかを具体的に観察することは、こうした宗教と経済の複雑な相互関係の一端を解明する一助となるだろう。
◆本企画の目的・方法:「宗教組織の経営」に注目する
経済に注目して宗教実践をみるという試みを行うにあたって、本企画で具体的に取り扱うのは「宗教組織の経営」という問題である。信徒個人ではなく、信徒集団としての宗教組織に注目するのは、その方が研究対象を限定しやすいという実際的な理由による。つまり各宗教の信徒たちが、上述したような教義的理想と経済的ジレンマにどのように対処しているかという問題を、宗教組織の経営という問題を通して具体的に検討する。
宗教組織の宗教実践とは、布教活動と表現できる。つまりあらゆる宗教組織は、何らかの宗教的・教義的な理想を実現・普及することを目指して活動している。しかし先述したとおり、現実の社会で布教活動をするためには、相応の財(経営資源)が必要である。一方で財の獲得・利用方法については様々な教義的な制約がある。こうした教義的理想と経済的現実のジレンマの中で、宗教組織はどのように経営資源を獲得・使用し、どのような布教活動を行っているか。つまりどのように経営されているか。本企画ではこの問題を、ブルキナファソのコーラン学校(清水発表)とミャンマーの上座仏教僧院(藏本発表)を事例として具体的に検討する。それによってコーラン学校/上座仏教僧院の実態を明らかすることを目的としている。
またこの問題を検討するにあたって、特に都市というコンテクストを重視する。本企画で扱う二つの宗教組織はともに、伝統的に村落社会を主要な経営基盤としてきた。しかし近年の急激な都市化は、宗教組織を取り巻く環境を大きく変化させつつある。こうした都市という環境の中で、コーラン学校/僧院はどのように経営されているのか。そこにはどのような問題があるのか。都市化は、現代社会においては不可避の趨勢である。したがってこの問題を検討することは、コーラン学校/僧院の布教活動、つまりムスリムや上座仏教徒(出家者)の宗教実践の未来を占う上でも重要な意義をもつだろう。
(文責:藏本龍介)
<都市>を生きる出家者たち
――上座仏教徒社会ミャンマー・ヤンゴンの僧院経営――
藏本龍介(東京大学大学院総合文化研究科博士課程)
本発表の目的は、ミャンマーを事例として上座仏教僧院の経営という問題を検討することによって、現代社会における上座仏教僧の仏教実践のダイナミズムを浮き彫りにすることにある。
上座仏教僧院(以下、僧院)とは、「無執着」という上座仏教の理想を実現することを目的とする出家者の共住集団である。この目的を達成するために、出家者は上座仏教教義、特に出家者の規則である「律」(ヴィナヤ)によって、経済活動や生産活動が禁じられている。つまり僧院を経営するために必要な諸々の資源を自ら獲得することができない。したがって在家者からの布施に依拠するという経営スタイルをとっている。しかし布施というのは要するに与え手の善意に基づくものであるため、経営基盤としては不安定なものである。こうした原理的なジレンマを抱える僧院は、実際にどのように経営されているのか。
この問題は、上座仏教徒社会に関する人類学的な研究において、長らく明示的な問題となってこなかった。なぜならこれらの先行研究においては、出家者が国家レベル/村落レベルにおいて社会に不可欠な役割を果たすがゆえに、在家者(世俗権力/村人)からの布施を受けるという、出家者と在家者の互酬的な共生モデルが前提とされていたからである。つまり僧院が布施を受けるのは自明のこととされた(石井 1975; Gombrich 1971; Spiro 1970; Tambiah 1976など)。
しかし「近代化」と総称されるような社会変動は、こうした自明性を掘り崩している。王国から国民国家への移行、市場経済の進展に伴い、僧院を取り巻く環境も大きく変化した。それは一言でいえば、僧院の民営化・市場化である。僧院の経営基盤は、旧来の①パトロン型(国家)や②コミュニティ型(地縁共同体)から、③マーケット型(市場)へと急速に移行しつつある。僧院は、こうした市場的環境――本発表ではこれを<都市>と表現する――にどのように対応しているのか。
この問題についてはタイ都市部を事例として、「黄衣ビジネス」と揶揄されるような護符の商品化(Tambiah 1984; 林 2000)や、瞑想法の簡易化・組織化によって多くの信徒・資金を集めたタンマガーイ寺についての分析などがみられる(矢野 2006など)。ただしこれらは特殊事例の分析に留まっており、<都市>を生きる出家者たちの実態が明らかになっているとは言い難い。そこで本発表では、1990年代以降、急激な都市化を経験しているミャンマー最大都市ヤンゴンを事例にその具体的様相を検討する。
発表の前半では、都市僧院の布施調達活動の実態とその問題について、俯瞰的に整理する。発表の後半では、律の遵守を目指す原理主義的な二つの僧院に対象を絞り、そうした試みがどのように展開したかを紹介する。こうした検討を通して、教義的理想(律の規定)と経済的現実のジレンマがどのように表出し、それに対してどのような試行錯誤がなされ、そこにどのような問題があるのかを整理する。それによって出家者の仏教実践が多様化していく原理・メカニズムを描き出したい。
『タリベとコーラン学校のモビリティ:ブルキナファソの事例から』
名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程
清水貴夫
ムスリム社会であるブルキナファソにおいては、都市化の流れに伴い、一般的に「ストリート・チルドレン」と呼ばれる少年たちの姿が目立つようになった。ブルキナファソ社会行動省の調べによれば、その44%が、コーラン学校の生徒タリベTaribéだという(Ministre de l'action sociale et de la solidarite national
2002 Programme national d'action educative en milieu ouvert2003-2007)。本研究の発端は、コーランを学ぶ少年たちのはずのタリベがなぜストリートに繰り出すことになったのか、ということであり、コーラン学校が「ストリート・チルドレン」の発生にいかようにかかわるのかということへの疑問である。本発表では、この問題に対し特にコーラン学校の経営の変容を通して、なぜタリベが社会問題化されたのかを検討する。
コーラン学校は、そもそも外来宗教であるイスラームがこの地域に浸透する過程で、この地域にとっては初めての体系的な教育システムとして各所に設置されてきた。いわゆる伝統的社会においてもこの制度は広く受け入れられてきた。伝統社会におけるコーラン学校は、畑を所有し、タリベとマラブー(導士)がともに働いて自給自足を行っていた。そして、タリベの親や地域の富裕者層からのタリーカ(喜捨)による金品の贈与、この二つの収入獲得手段によってコーラン学校が支えてきた。これが一つのコーラン学校のプロトタイプとして、この地域の人びとに認識されている。
しかし、このコーラン学校を取り巻く環境は大きく変容している。ひとつは近代的な教育システムの普及によって、コーラン学校の地位が相対的に低下したことによる。現在のブルキナファソにおいては、マドラサ、フランコ=アラブ、コーラン学校の3つの学校形態が存在し、CMBF、およびムスリム富豪による支援はマドラサとフランコ=アラブに集中している。より私的な組織でマラブーが個人で経営する、いわば寺小屋的なコーラン学校は、独自の収入源を求めなければならない。
もうひとつは村落部の変容である。CMBFなどから毎年決まった支援を受けたことのない村落部のコーラン学校では、地域社会がマラブーに使用させる土地での自給自足がコーラン学校の運営の基礎となる。これに喜捨が加わってコーラン学校が成立していた。しかし、村落部の人口圧力や不安定な農業生産、さらに貨幣経済の比重が重くなることにより、従来のコーラン学校のシステムにひずみが生じ、村落での持続的な運営は困難になっていく。
このためコーラン学校は、より資源獲得の可能性が高い都市へと移動を繰り返す。実際に、多くのコーラン学校が数年単位、時に数カ月単位で拠点を移しながら、最終的に大都市、ワガドゥグにたどり着くこととなる。都市に移動したとしても、コーラン学校は従来のシステムを踏襲できるわけではない。マラブーは、様々な運営努力をする中で、宗教的な要請から外れていると認識しつつも、タリベたちにストリートで「喜捨」を集めさせる。こうした、タリベの行為は、物乞いをする少年たち、つまり「ストリート・チルドレン」として見做されるようになる。
このようにブルキナファソにおける「ストリート・チルドレン」問題は、新たな経済的現実に「喜捨」を集めるという方法で対処しようとするコーラン学校の経営形態と密接に結びついている。本発表ではこの事象を、現代ムスリム社会における宗教と経済の相互関係を示す一事例として提示してみたい。
◆参照文献
ウェーバー、マックス 1989(1902~1903)『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(大塚久雄訳)岩波書店。
大塚和夫 2000 『近代・イスラームの人類学』東京大学出版会。
大塚和夫(編)2002 『現代アラブ・ムスリム世界』世界思想社。
カサノヴァ、ホセ 1997 『近代世界の公共宗教』(津城寛文訳)玉川大学出版部。
ゲルナー、E. 1991(1981)『イスラム社会』(宮治美江子ほか訳)世界思想社。
ゴンブリッチ、リチャード & ガナナート・オベーセーカラ 2002(1988)『スリランカの仏教』(島岩訳)法藏館。
田辺繁治(編) 1995 『アジアにおける宗教の再生: 宗教的経験のポリティクス』京都大学学術出版会。
マルクス、カール 1956(1859)『経済学批判』(武田隆夫ほか訳)岩波書店。
Leach, Edmund R. (ed.) 1968 Dialectic in practical religion. Cambridge papers in social anthropology Vol.5. Cambridge: Cambridge University Press.
Redfield, Robert 1956 Peasant society and culture: an anthropological approach to civilization. Chicago: University of Chicago Press.
Tambiah, Stanley J. 1970 Buddhism and the spirit cults in Northeast Thailand. Cambridge: Cambridge University Press.
◆参考文献[藏本発表]
石井米雄 1975 『上座部仏教の政治社会学』創文社。
林行夫 2000 「現代タイ国における仏教の諸相:制度と実践の狭間で」『現代世界と宗教』総合研究開発機構・中牧弘允(編): 71-87 国際書院。
矢野秀武 2006 『現代タイにおける仏教運動:タンマガーイ式瞑想とタイ社会の変容』東信堂。
Gombrich, Richard F. 1971 Buddhist precept and practice: traditional Buddhism in the rural highlands of Ceylon.(2nd ed.1991)Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.
Spiro, Melford E. 1970 Buddhism and society: a great tradition and its Burmese vicissitudes. New York: Harper & Row.
Tambiah, Stanley Jeyaraja 1976 World conqueror and world renouncer: a study of Buddhism and polity in Thailand against a historical background. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
Tambiah, Stanley Jeyaraja 1984 The Buddhist saints of the forest and the cult of amulets: a study in Charisma, Hagiography, Sectarianism, and Millennial Buddhism. Cambridge: Cambridge University Press.
◆参考文献[清水発表]
Coquery-Vidrovitch, Catherine 1993 Histoire des villes d’Afrique noire: Des origins à la colonisation Albin Michel
Enda tm jeunesse action (出版年不明)Taribé au Burkina Faso, de l’étude à l’action
ゲルナー, アーネスト1981(1990)『イスラム社会』(宮治美江子・堀内正樹・田中哲也訳)紀伊国屋書店
飯森嘉助 1992「都市と教育」板垣雄三・後藤明(編)『事典 イスラームの都市』亜紀書房
陣内秀信・新井勇治(編)2002『イスラーム世界の都市空間』法政大学出版
LEVZION, Nehemia 1968 MUSLIMS AND CHIEFS IN WEST AFRICA : A STUDY OF ISLAM IN THE MIDDLE VOLTA BASIN IN THE PRE-COLONIAL PERIOD, OXFORD AT THE CLARENDON PRESS
Naba Jérémie WANGRE et Alkassoum MAIGA 2009 Enfants de rue en Afrique L’Harmattan
大塚和夫 1989『異文化としてのイスラーム』同文舘
坂井信三 1995「文書活動と宗教的イデオロギー―19世紀西スーダンのジャの事例から」杉本良夫(編)『宗教・民族・伝統 イデオロギー論的考察』南山大学
坂井信三 2003『イスラームと商業の歴史人類学 西アフリカの交易と知識のネットワーク』世界思想社
嶋田義仁 1994『異次元交換の人類学-人類学的思考とはなにか-』勁草書房
Skinner, Elliot 1964 The Mossi of The Upper Volta Stanford University Press
Skinner, Elliot 1966 Islam in Mossi Society “Islam in Tropical Africa” Indiana University Press
Skinner, Elliot 1974 African Urban Life, Transformation of Ouagadougou Prinston University Press
ZAMPO, Lassina 2007 L’école coranique migrante, une pratique éducative en questione : cas des écoles colaniques de la commune de Ouagadougou au Burkina Faso Mémoire de fin d’études présenté en vue de l’obtention du grande de licencié en politique économique et sociale, Université Catholique de Louvain